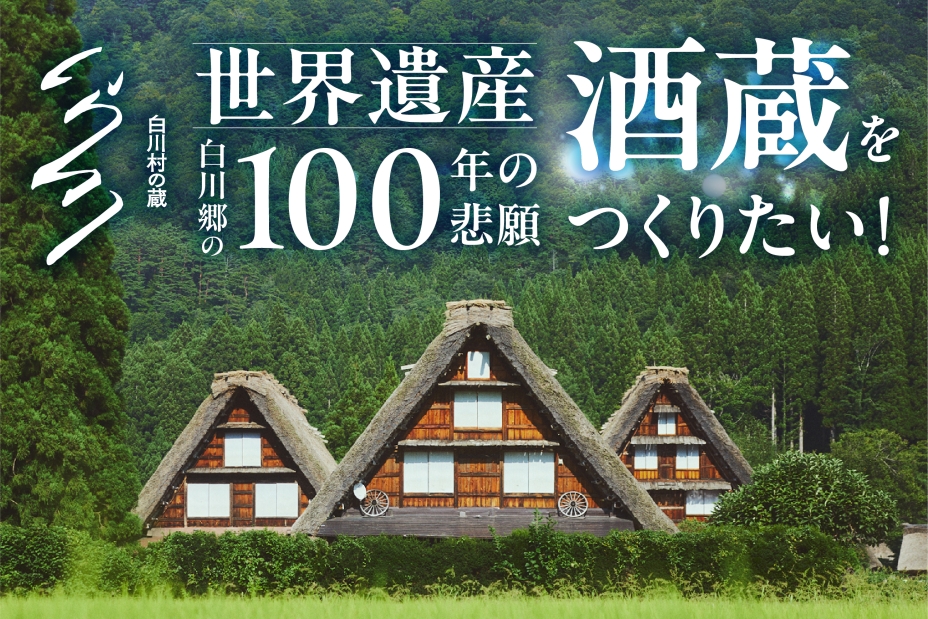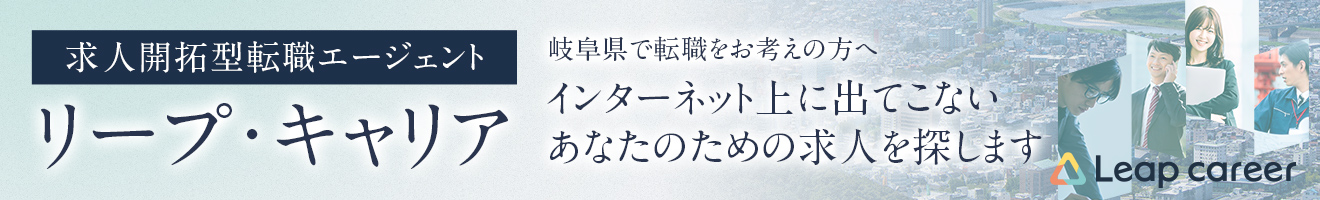Leader's Voice
「安心」と「ワクワク」に溢れた「人やモノが集まる岐阜県」の実現へ

Interview
江崎 禎英 岐阜県知事
新県政をスタートさせた江崎禎英岐阜県知事に、岐阜県への思いや将来像について語っていただきました。「政策の課題も答えも現場にある」という思いを胸に、県民の皆さんと一緒に岐阜県の未来を創ろうとされています。子どもや若者たちにも「県政をより身近に感じて欲しい」と呼びかけています。
いち早く日本の社会課題に取り組み、モデルとなるような政策を岐阜県から発信する
―― 知事を志した理由を教えてください。
江崎知事 現在、日本社会は様々な面で行き詰まりを見せており、多くの方々が将来への不安や閉塞感を感じています。そのため、教育も働き方も農業も林業も、変わらなければいけないタイミングに来ています。
「現状維持」は「衰退」です。県民の皆様と共に不安や閉塞感を払拭し、5年後、10年後に全国に誇れる岐阜県を創っていきたいと考え、知事を志しました。

―― これから知事として目指していきたいことを教えてください。
江崎知事 私はこれまで、県で実施した仕事がその後に国の政策になるという経験をしてきました。日本が直面する課題について、いち早く岐阜県が取り組み、日本のモデルになるような政策を発信することで、若い人たちが夢と誇りをもてる岐阜県にしてまいります。
2021年の県知事選挙以来、約4年間、県民の皆様の声を直に聞く中で「政策の課題だけでなく、その答えも現場にある」という確信を得ています。幸いなことに、岐阜県は日本の真ん中に位置しており、豊かな自然、多種多様な食材、世界に誇るべき歴史や伝統文化など、実に多くの魅力が揃っています。
こうした強みを活かし、日本社会が直面する様々な課題に果敢に挑戦し、「安心とワクワク」に溢れる政策を発信することで、「人やモノが集まる岐阜県」の実現を目指してまいります。
―― 今の岐阜県をどのようにみられていますか。
江崎知事 岐阜県は日本の真ん中にあって、自然環境が豊かで、土地や物価が安く、暮らしやすく、交通網が整備されていることから、本来、人口増加が見込めそうですが、実態は真逆です。
加速する少子高齢化や、混沌を極める国際情勢、激甚化・頻発化する自然災害、さらには、円安に伴う物価の上昇など、多くの方々が将来に対して不安や閉塞感を感じています。こうした日本社会において、岐阜県だからこそできること、やらなければならないことがあります。
―― やらなければならないこととは?
江崎知事 一つは子どもたちが安心して暮らすことのできる未来を創るために、子どもたちが感性を磨き生きる力を高めることのできる教育環境をつくること、もう一つは高齢になっても、障がいがあっても、社会で活躍できる雇用のあり方を見直すこと。そして、食料とエネルギーの自給率を高めることです。
―― そのためにどのようなことが必要だと思われますか?
江崎知事 「意識改革」と「地域の協力」です。これまでの「あたりまえ」を見直し、今の知識や常識に捉われることなく、何が本当に必要かを掘り下げることが必要です。そして、県内にある資源を十分に活かし、より多くの視点で物事を捉え、地域と連携して課題の解決に取り組みたいと考えています。
具体的には、知事として掲げている「10の目指すべき目標」の実現に向けて取り組みます。そして、これから求められる社会経済システムや新しい社会のルールを作り、未来につながる政策を発信することで、日本中、さらには世界から注目される岐阜県にしてまいります。
課題解決に向けてまとめた「10の目指すべき目標」の実現へ
―― 「10の目指すべき目標」について、1つずつお話しいただけますか。
江崎知事 これまでに県民の皆様から直接伺った様々なご意見の集大成が「10の目指すべき目標」です。課題を解決するべく、次のような取り組みを進めていきます。
1.若者や女性が持てる力を発揮できる働き方や職場をつくる
若者、とりわけ若い女性の流出が顕著である背景には、男性、女性といった性差に関する偏見や、古い価値観の押し付けなど、若者や女性の意見が反映されにくく、活躍の場が見出せないといった点が指摘されています。
こうした状況を改めるため、企業の皆様のご協力の下、残業を前提とした長時間労働のあり方を見直し、子育て中の女性や、多様な価値観を持った若者などがやりがいをもって働き、十分な収入を得る機会を創出する「働いてもらい方改革」を進めてまいります。
これにより、地域の中小・小規模事業者が直面する人手不足の問題にも対応していくほか、将来的には、マイクロワークの導入といった柔軟な雇用形態の実現など、若者や女性に選ばれる地域づくり、更には、高齢者や障がいのある方にとっても働きやすい、持続可能な社会の実現に取り組んでまいります。
2.子どもを産み育てやすい環境やサポートシステムをつくる
少子化の問題に関し、まずは、現在急速に増えつつある産後うつなどの問題に対応するため、安心して子どもを産み育てられる環境を整備してまいります。
具体的には、結婚から妊娠、出産、育児まで、ライフステージに応じたサポートシステムを構築するとともに、男性の育休活用を促進するなど、家事・育児・介護等を男女が共に担うライフスタイルを促進し、将来的には、子どもや子育て世代を地域や社会が一体となって支える岐阜県をつくってまいります。
3.お年寄りや障がいがある方が活躍できる場や居場所をつくる
「人生100年時代」と言われる今日においては、高齢者が健康で生きがいを持って活躍できる環境、特に、一人暮らしの高齢者が家に閉じこもることなく、地域との関わりを持ち続けられる場の提供が重要です。
また、障がいの有無に関わらず、その方の希望や能力、適性を十分に活かして、共に働き、暮らしていく社会を実現することが求められています。 そのため、高齢者や障がいのある方が、それぞれに相応しい働き方ができるよう、企業における業務の切出しや細分化など、柔軟な雇用形態を推奨してまいります。
さらに、文化の伝承や地域社会の維持管理、農作業など、高齢者や障がいのある方が地域のコミュニティで活躍できる場を市町村と共に生み出してまいります。
4.災害などに強いインフラや医療・防災システムを整備する
激甚化・頻発化する豪雨災害や、南海トラフ巨大地震など大規模地震の発生に備え、災害時にも社会機能が維持されるよう、道路や河川などの計画的な整備、上下水道など老朽化が進むインフラ施設の計画的な改修を進めてまいります。
また、大規模災害の発生時に県民の皆様の命を守るため、防災教育など「自助」の実践、そして、自治会など地域ぐるみの防災訓練や避難所運営支援などによる「共助」の強化を進めてまいります。
さらに、県内の医療資源を見直し、他県との連携も図りながら災害時の医療救護体制を充実させてまいります
5.鳥獣害のない里山を作り多様な価値を生む農業を推進する
個々の農家による鳥獣害対策には限界があり、地域全体で連携して対策を行う体制が必要である一方、野生鳥獣は、生物多様性や動物愛護の観点から、適切に保護、管理することも必要です。
このため、野生鳥獣の生息域の確保による生態系の保全を図りつつ、ドローンや人工衛星など最新の技術も用いながら、鳥獣害を効果的に減少させる先進的なモデルとなる対策を確立してまいります。
さらに、有機、農薬不使用など環境調和型の農業の推進、農村の魅力を活かした体験型教育、高齢者や障がいのある方の活躍の場、観光としての農業の推進など、農業全体の付加価値と収益性を高めてまいります
6.山林や堆肥などを活用したクリーンなエネルギーを供給する
山林の所有者が確定できないため、効率的な林道の整備や計画的な木材の搬出が難しいといった課題に対し、山林管理に係る新たな制度構築を行います。
さらには、木材の生産だけでなく、木質バイオマス燃料に加え、端材や枝葉、堆肥等から生産する「バイオコークス」といったカーボンニュートラルな新エネルギーを開発・供給する体制の確立など、森林資源の利用を拡大し、林業の持続性を高める対策を進めてまいります。
このほか、太陽光や小水力、地熱など、地域の資源を活用して、地域に必要なエネルギーを供給する体制を構築し、2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにする「脱炭素社会ぎふ」の実現を目指してまいります。
7.中堅中小企業の生産性を高め伝統産業の価値を発信する
県内の中堅中小企業は、本県の経済を支える重要な存在である一方、労働条件や福利厚生が大企業に比べて見劣りする、あるいはそこで働く人々にとって長期的なキャリアビジョンが持ちにくいなどの理由から、人材の確保が困難になっています。
特に伝統産業においては、かつての商習慣が依然として存続しているケースが多く、ビジネスモデルを転換し、企業イメージを向上させることが必要です。
幸い本県には、歴史に培われた伝統産業が数多く根付いており、これらの魅力を発見・発信し、認知度を向上させるとともに、その匠の技を継承していくため、観光と連動したストーリー性のある情報発信、あるいは現代のデザインとの融合など、その価値の創造、拡大に努めてまいります。
8.社会課題を解決し未来を拓く新たなビジネスや産業を生み出す
農業者の高齢化や後継者不足等によって増加する耕作放棄地、あるいは人口減少に伴って増える空き家などの問題については、教育や観光、地域振興、防災など、多様な視点から活用に向けてアプローチすることで、課題の解決を図ります。
また同時に、地域と連携した教育、観光誘客、地域コミュニティの深化や防災拠点の確保など、様々な効果をもたらすことが考えられます。 特に、大都市名古屋に隣接する地の利や、リニア中央新幹線、東海環状自動車道といった交通ネットワークを活用して、新たなビジネスを生み出す取組みを支援してまいります。
さらには、鳥獣害対策や山林資源の活用など、先端技術を取り入れることで、全国的に展開できる産業の構築も推進してまいります。
9.豊かな感性を育み多様な子どもが一緒に学ぶ教育を実現する
子どもたちが生きる力を身に付けるには、主体的に学び、考え、失敗を恐れず、様々な経験を重ねることが重要です。一方、全国の小・中学校には、いじめや友人関係、学業など、様々な悩みを抱える約35万人の不登校の児童生徒がおり、専門家によるサポートや適切な教育プログラムの提供、居場所の確保などの支援を充実させることが求められています。
こうした状況に対応するため、学校や家庭、地域社会が連携して環境を整備し、地域の課題を発見・解決する学びを通して視野を広げ、自信や誇りにつながる教育を実現してまいります。
将来的には、社会の中で人と交わり、共に生活していくために必要なソーシャルスキル向上のため、異年齢の集団による教育活動を推進してまいります。
10.文化や芸術、スポーツなど人生を豊かにする活動を促進する
文化や芸術、スポーツといった分野に取り組む人口の減少により、その維持発展や、特にスポーツにおいては学校単位でのチームの編成が難しくなっています。
このため、県民の皆様が、日頃から文化・芸術・スポーツに親しむことができる環境を整備し、より豊かな生活を楽しむとともに、外国人も含めた県外の方々に魅力を感じてもらえるよう努めてまいります。
子どもも若者も参加できる「政策オリンピック」を実施中
―― 新たな政策を企画、立案、実施するための「政策オリンピック」とは、どのようなものですか。
江崎知事 「10の目指すべき目標」を実現するための新たな手法として、「政策オリンピック」を実施しています。効果が確認されたアイデアや手法については、必要な修正を加え、県の政策として他の地域に展開してまいります。 さらに、法制度の見直しが必要と考えられるものについては、国に対して積極的に政策提言するなど、日本の抱える課題に果敢に取り組んでまいります。
―― 「政策オリンピック」には、誰もが参加できるのでしょうか。
江崎知事 専門家や有識者だけでなく、将来を担う当事者である子どもや若者の皆様の柔軟な発想が必要です。 そこで、「政策オリンピック」の実施に当たっては、小中学生からも課題解決に向けたアイデアやその具体的な解決方法をご提案いただけるよう、分かりやすいテーマを設定し、より多くの方の参加を得たいと考えています。 こうした、自ら提案したアイデアで県政や社会を変えることができるといった体験を通じ、子どもや若者の皆様には、県政をより身近に感じていただくとともに、故郷に対する誇りと愛着を育んでいただきたいと考えています。
―― 最後に、岐阜県民のみなさんへのメッセージをお願いします。
江崎知事 これまでの「あたりまえ」を見直し、「安心」と「ワクワク」に溢れた「人やモノが集まる岐阜県」の実現のため、知事として力を尽くし、県民の皆様と共に未来を創ってまいります。